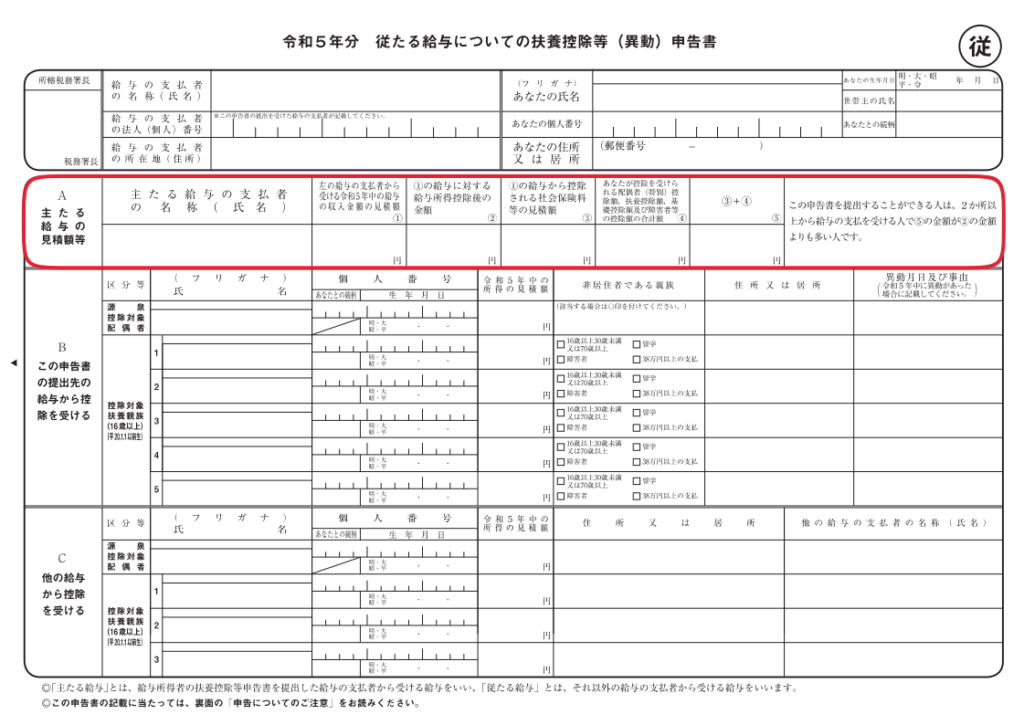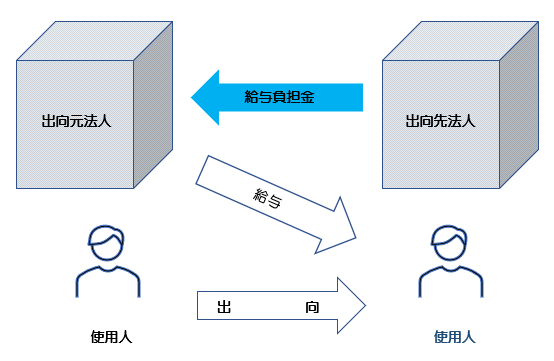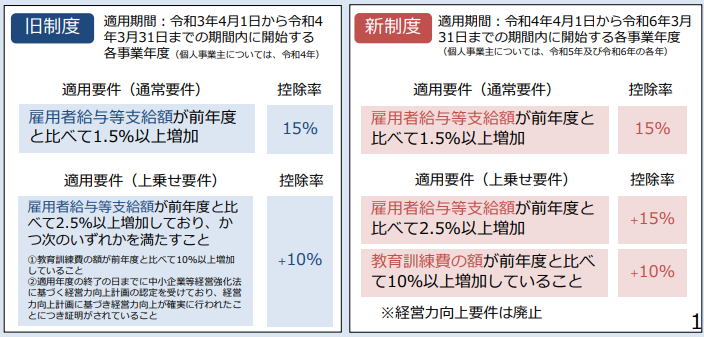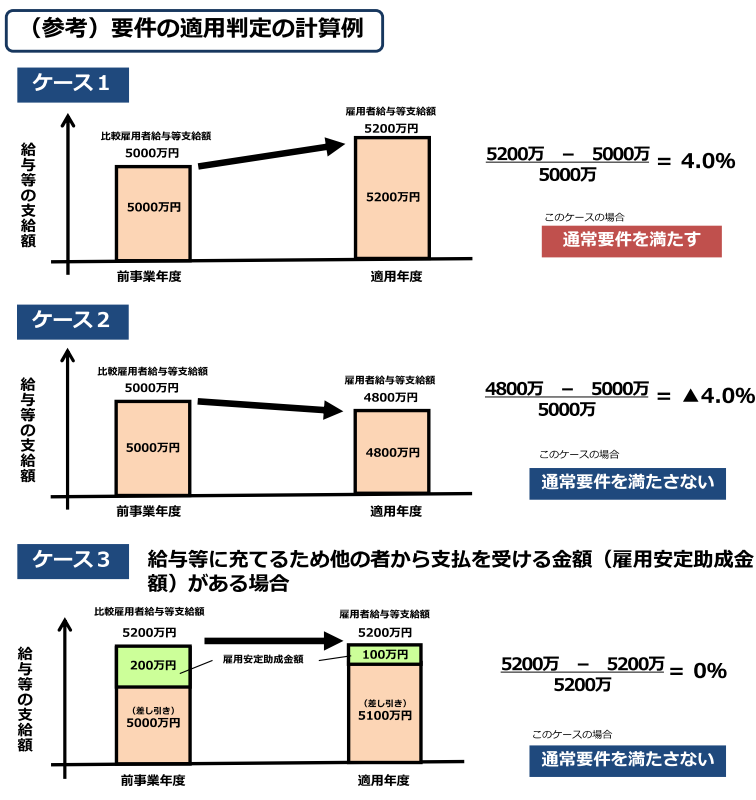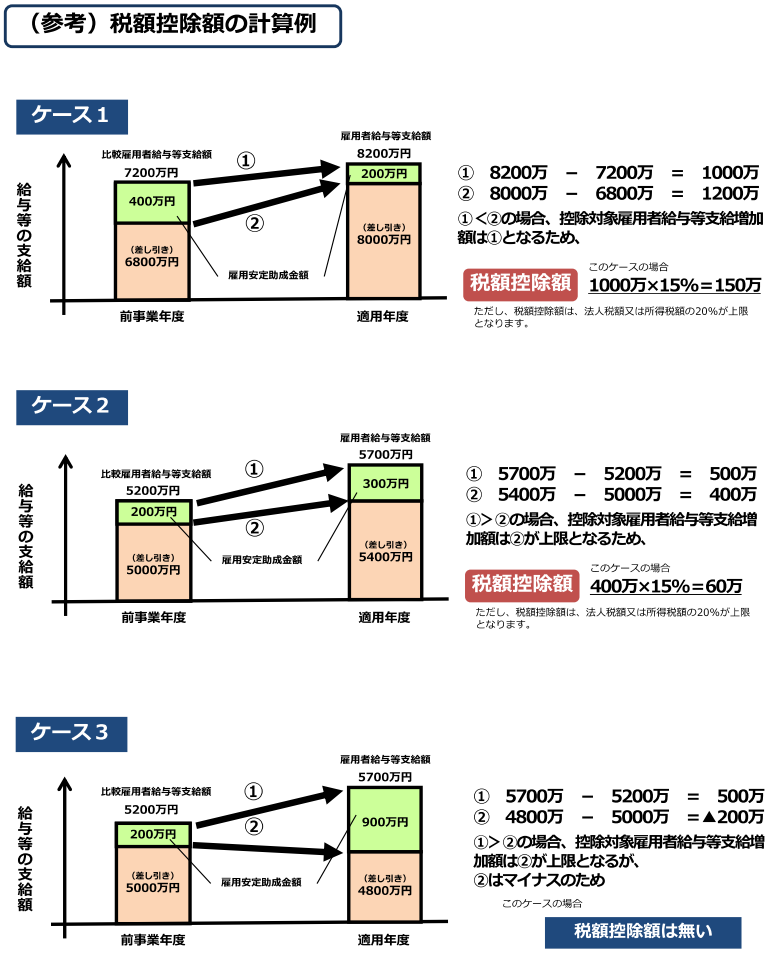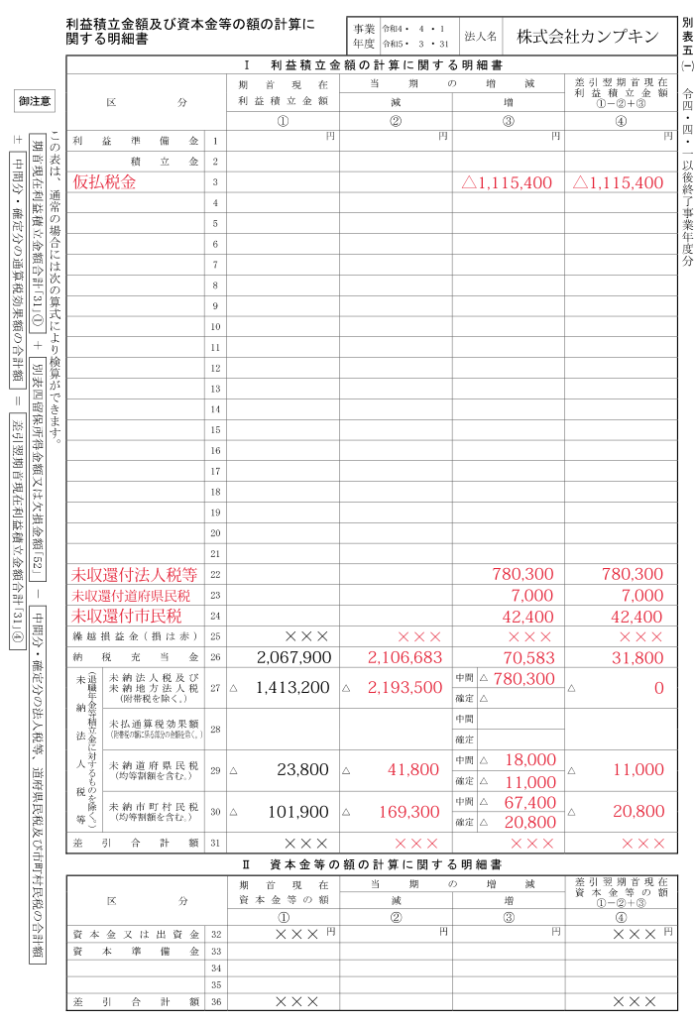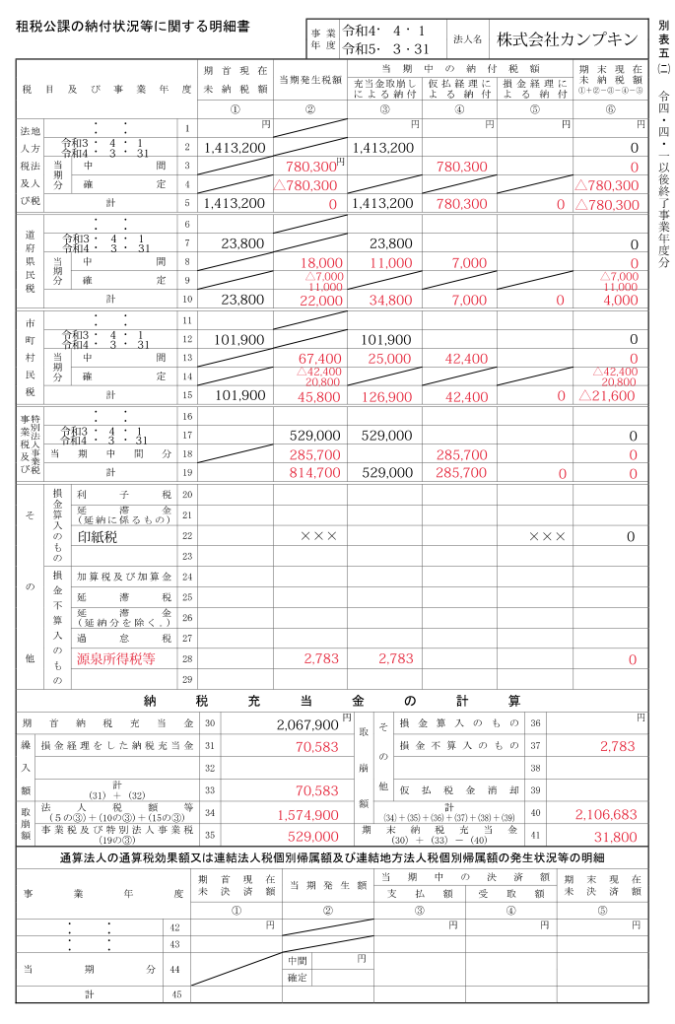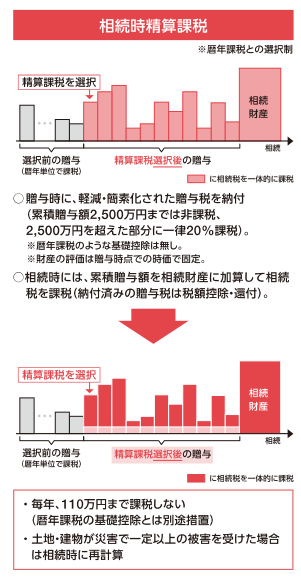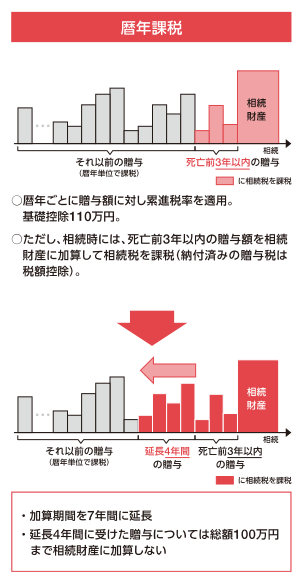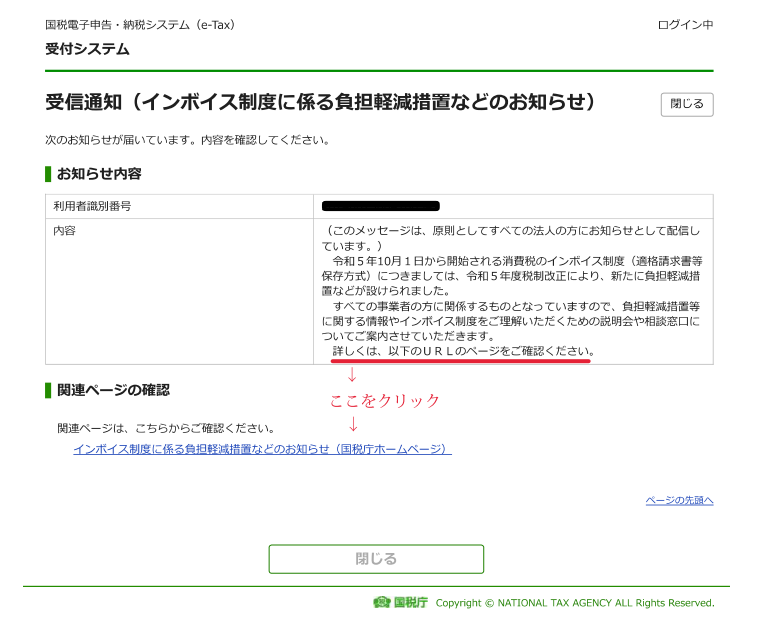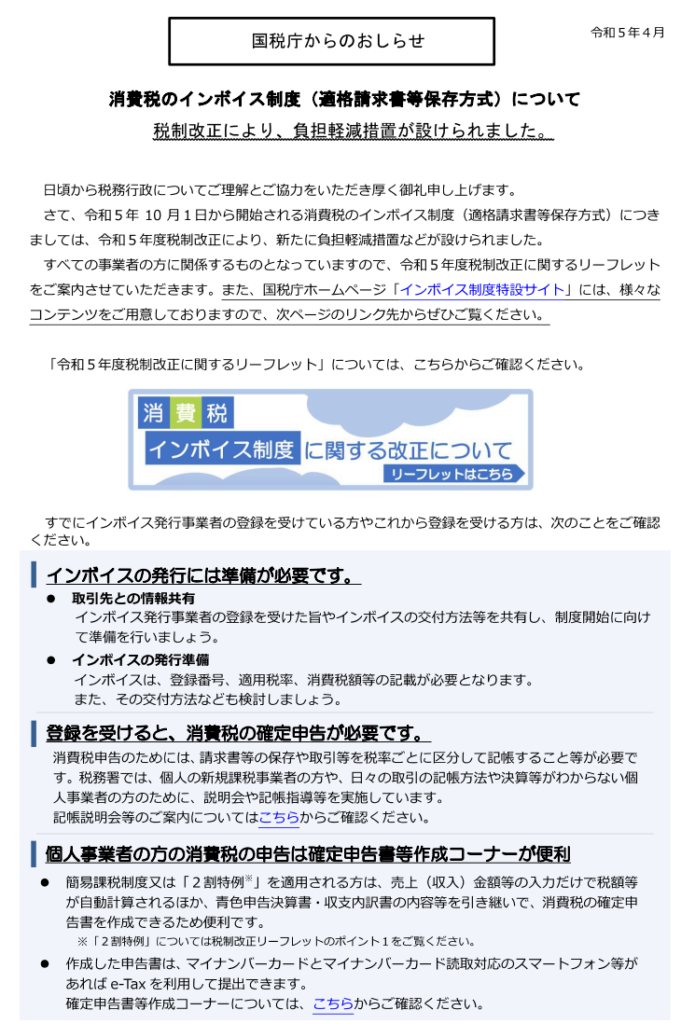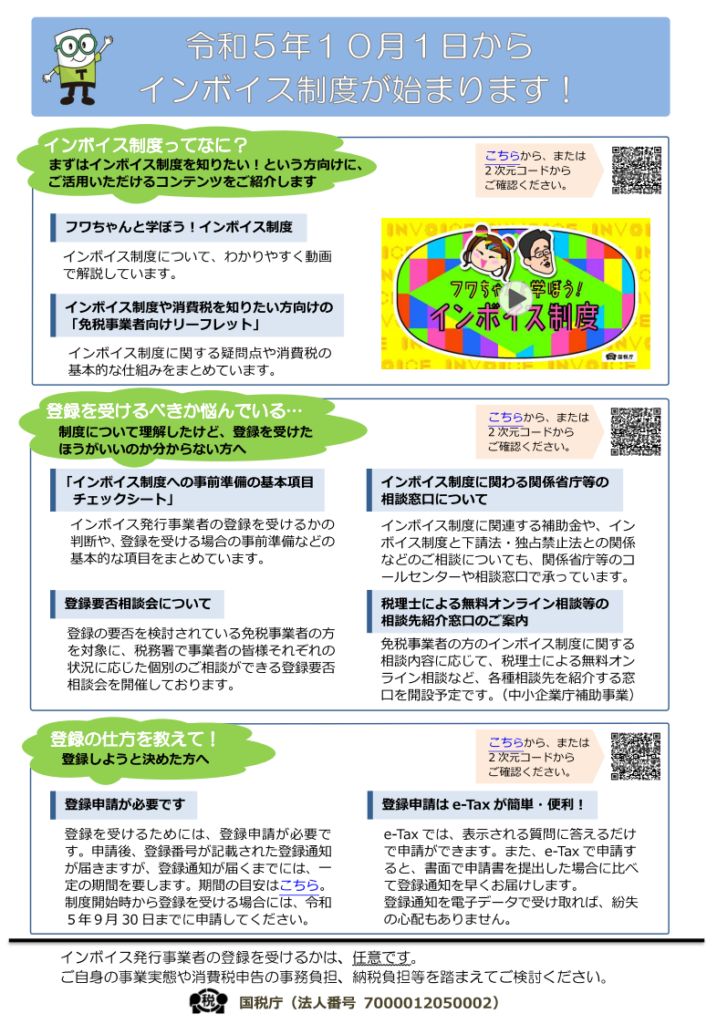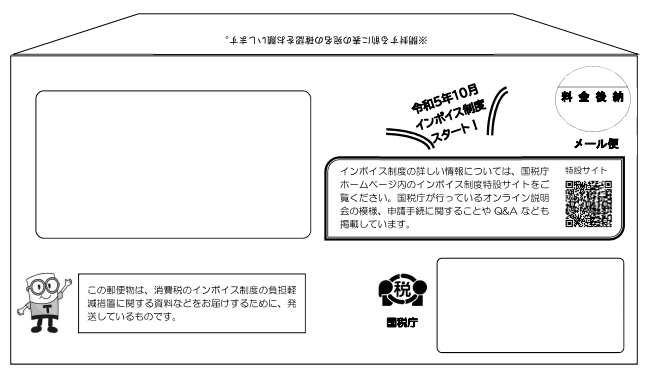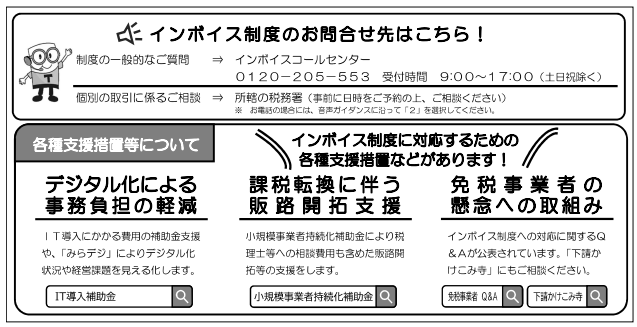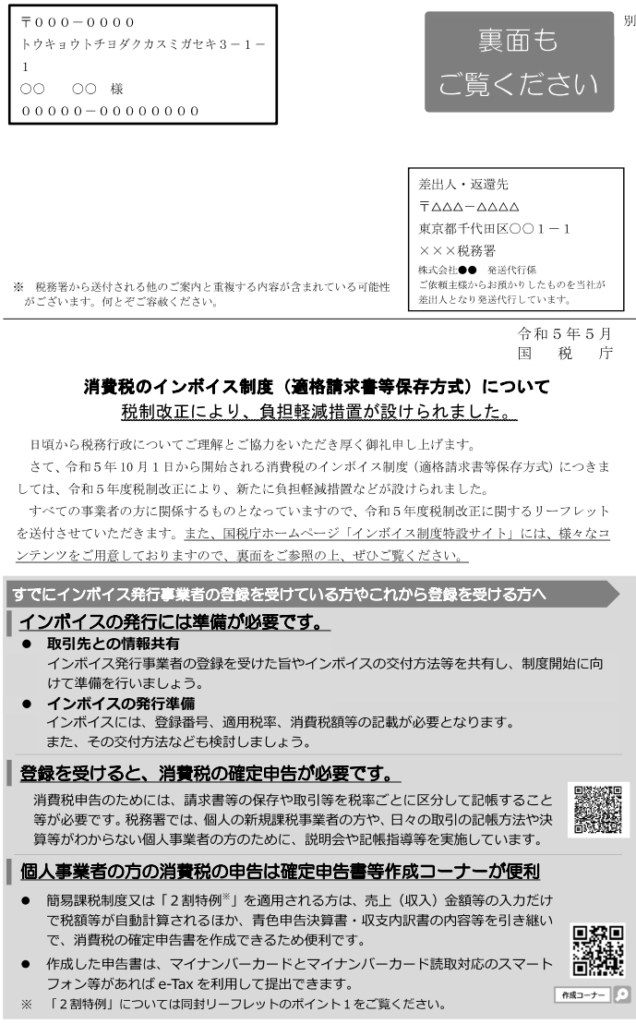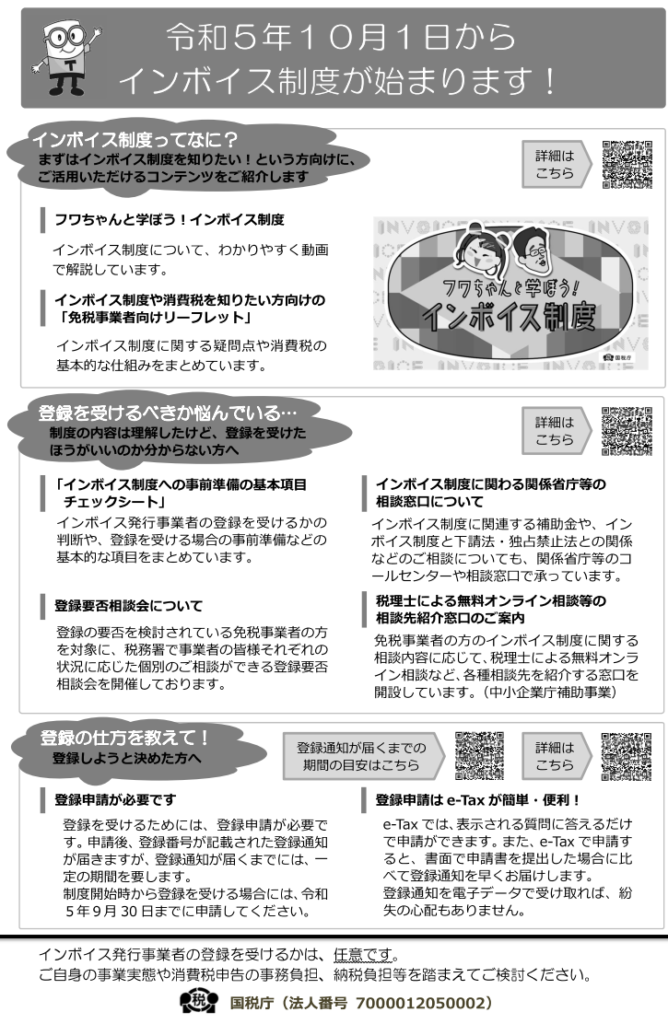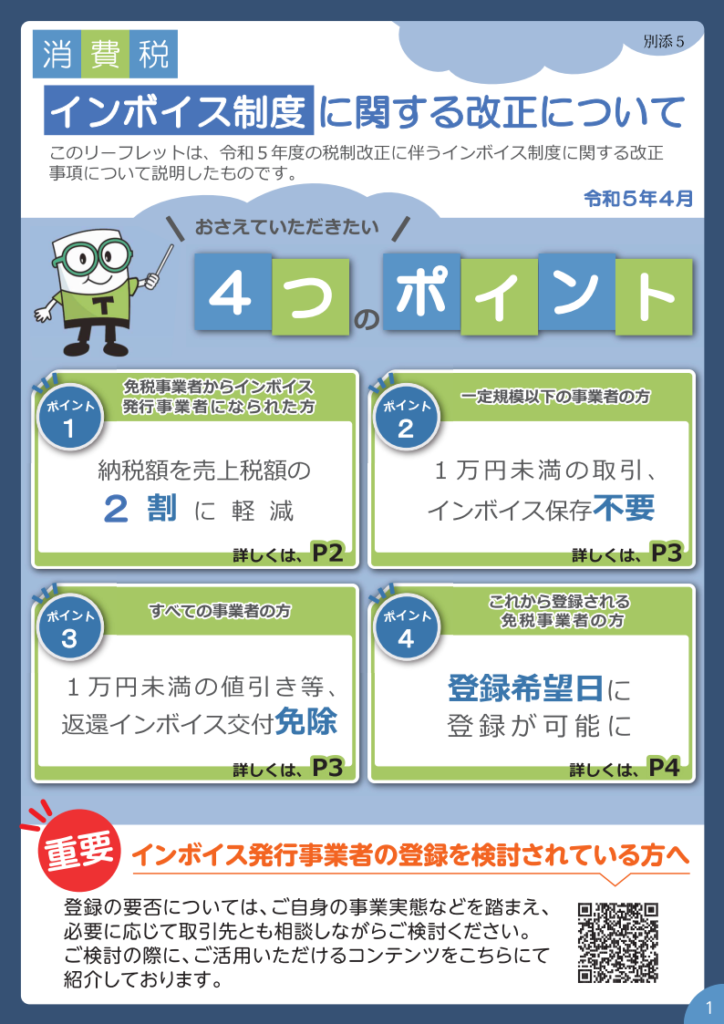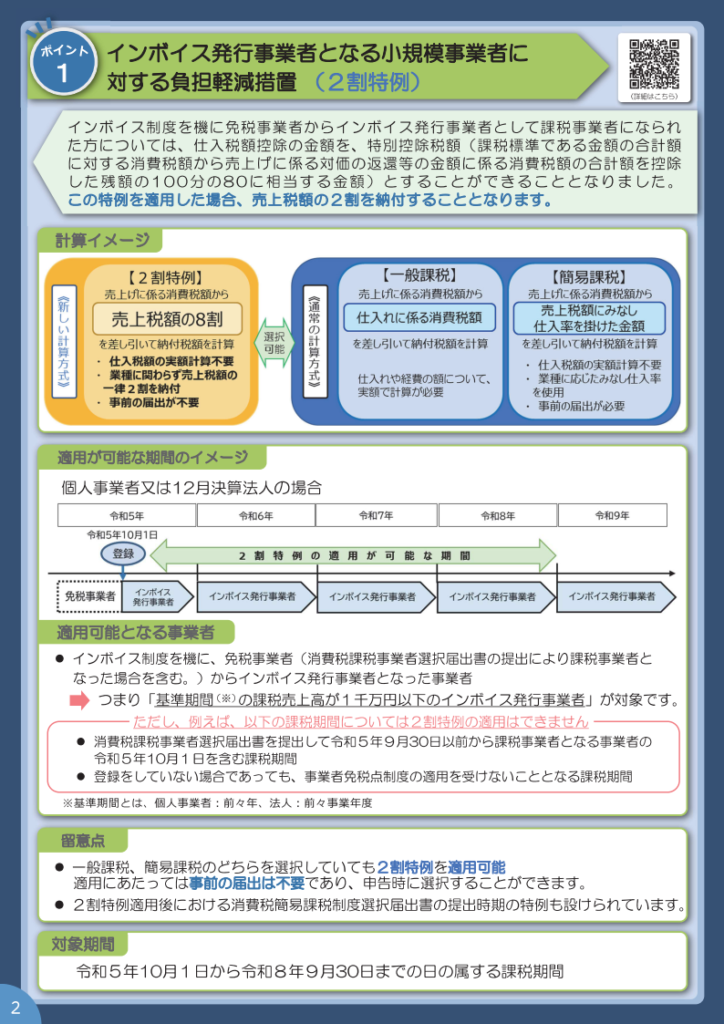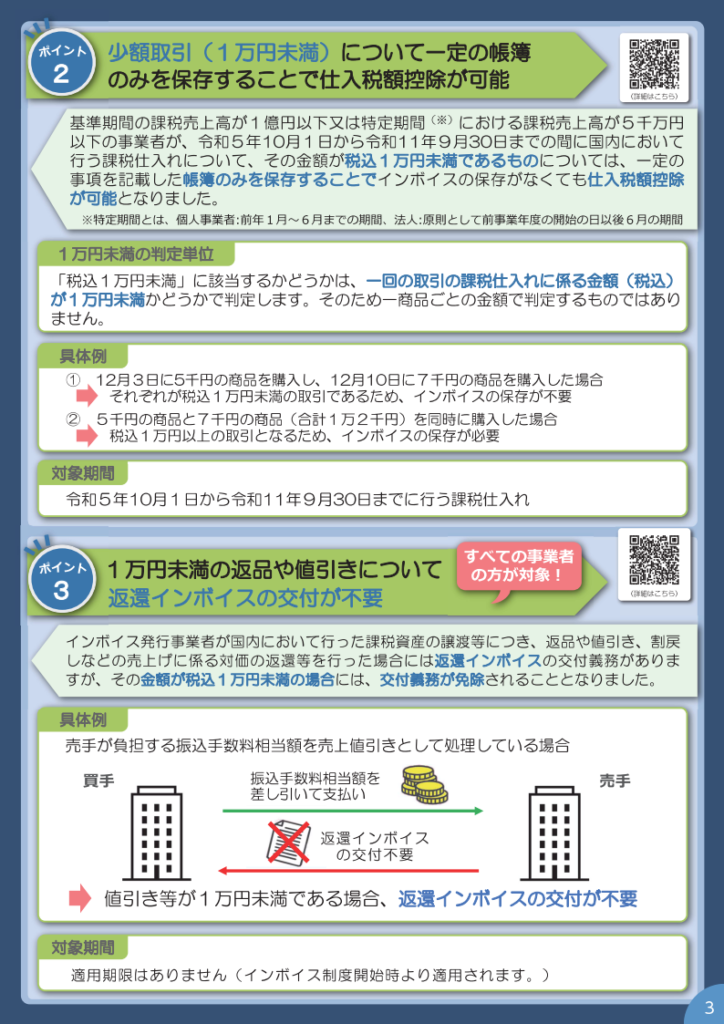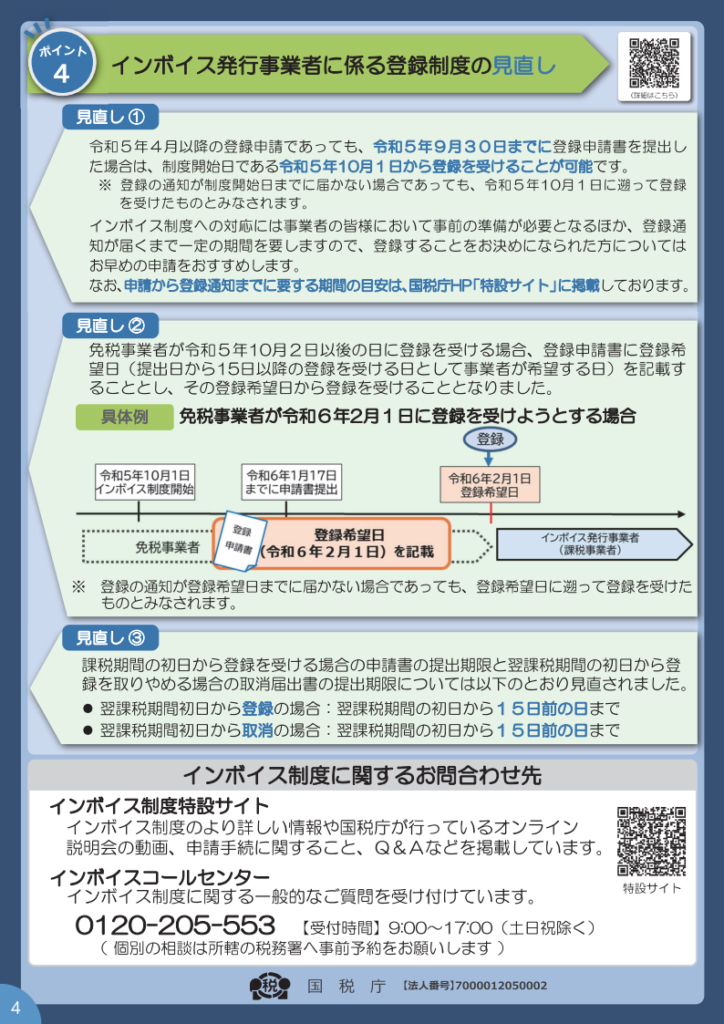1.丙欄で源泉徴収するための要件
パートやアルバイトで働く人に支払う給与は、日給(勤務した日)や時間給(勤務した時間)で計算することが多いと思われますが、これらの人に給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の従業員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます(源泉徴収税額表の月額表、日額表、甲欄、乙欄、丙欄の使い分けの判断基準については、本ブログ記事「源泉徴収税額表の『月額表』『日額表』の使い方と『甲欄』『乙欄』『丙欄』」をご参照ください)。
一方、パートやアルバイトの人の給与を日給または時間給によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。
(1) あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること
(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと
したがって、2か月以内の短期間(有期雇用)で募集するパートやアルバイトの人に対して日給や時間給で支払う給与は、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
パートやアルバイトで断続的に勤務する人に対して支払う給与について、日額表の丙欄を使って源泉徴収をすると、日額(その日の社会保険料等控除後の給与等の金額)が9,300円未満であれば源泉徴収税額は0円になります。
これは、同じ日額表の甲欄や乙欄を使って源泉徴収する場合よりも税額を抑えることができます(給与が日額9,200円以上9,300円未満の区分であれば、甲欄では250円(扶養親族等の数が0人の場合)、乙欄では1,530円の源泉徴収が必要です)。
ただし、丙欄で源泉徴収するための要件については、常に確認する必要があります。
2.契約期間や支払期間が2か月を超えた場合
前述したように、2か月以内の短期間(有期雇用)で募集するパートやアルバイトの人に対して日給や時間給で支払う給与は、次のいずれかの要件に基づき「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をします。
(1) あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること
(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと
(1)の要件については、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができず、「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。
なお、雇用契約の期間を2か月ごとに更新することとしている場合もあると思います。例えば、5月~6月の2か月を一つの雇用期間とし、この雇用期間が過ぎれば新たに7月~8月の2か月を一つの雇用期間として更新する場合です。
また、5月~6月の雇用契約が終了した後に、7月は雇用契約をせずに、8月~9月の2か月について新たに雇用契約する場合もあります。
一つ一つの雇用契約の期間を見れば2か月以内ですが、いずれの場合も雇用契約の期間の延長や再雇用に該当するため、2か月を超えると判断されます。つまり、「日額表」の「丙欄」は使えないということです。
(2)の要件については、日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこととなっています。
日雇賃金については、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をしますが、継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間に支払われるものは日雇賃金にはならず、「日額表」の「丙欄」は使えません。したがって、「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って源泉徴収をすることになります。
(2)の要件で少し気になるのは、「継続して」の部分です。
例えば、5月に8日間、6月に10日間雇い入れて日雇賃金を支払った後、7月は雇い入れずに、8月にまた雇い入れる場合、8月の給与は日雇賃金になるのでしょうか?
この場合の8月に支払う給与は、日雇賃金にはなりません。5月・6月と8月の間に1か月の空きがありますが、この場合も継続して2か月を超えて給与等が支払われたと判断されますので、8月に支払う給与については「日額表」の「丙欄」は使えません。
しかし、5月・6月はA社で日雇賃金が支払われ、8月はB社で給与が支払われる場合は、8月の給与は日雇賃金になり「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をします。
つまり、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われなければ、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をすることになります。
3.建設業従事者の特例
原則として、雇用契約の期間や日雇賃金の支払期間が2か月を超えると「日額表」の「丙欄」は使えませんが、建設業従事者の場合は、雇用期間等が2か月を超えていても8か月を超えなければ、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をすることになります。
具体的な要件は、次のとおりです(参考:国税庁ホームページ「建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について」)。
(1) 同一事業主に継続して雇用されることを常態としない
(2) 同一事業主に雇用される期間が継続して8か月を超えない
(3) 同一事業主に継続して1か年を超えて雇用されない