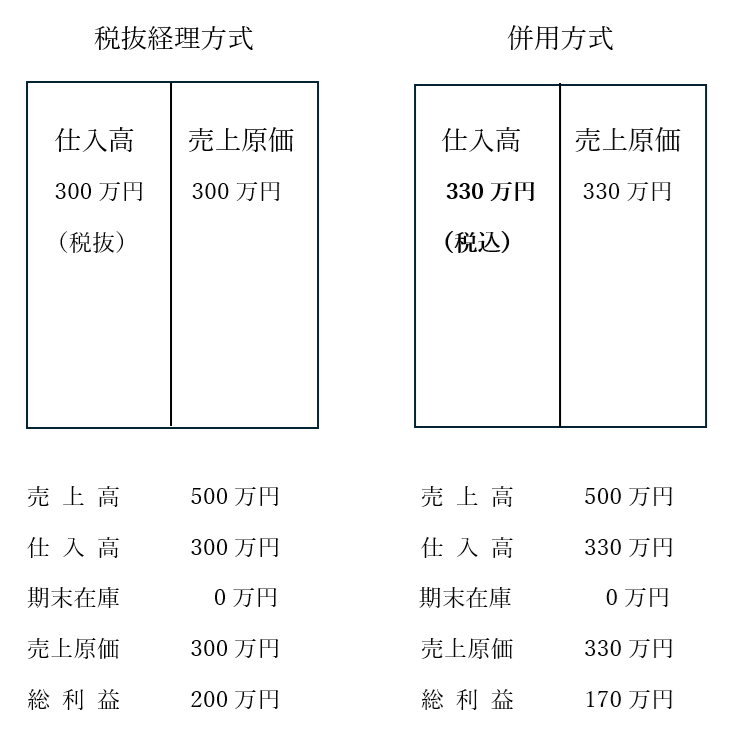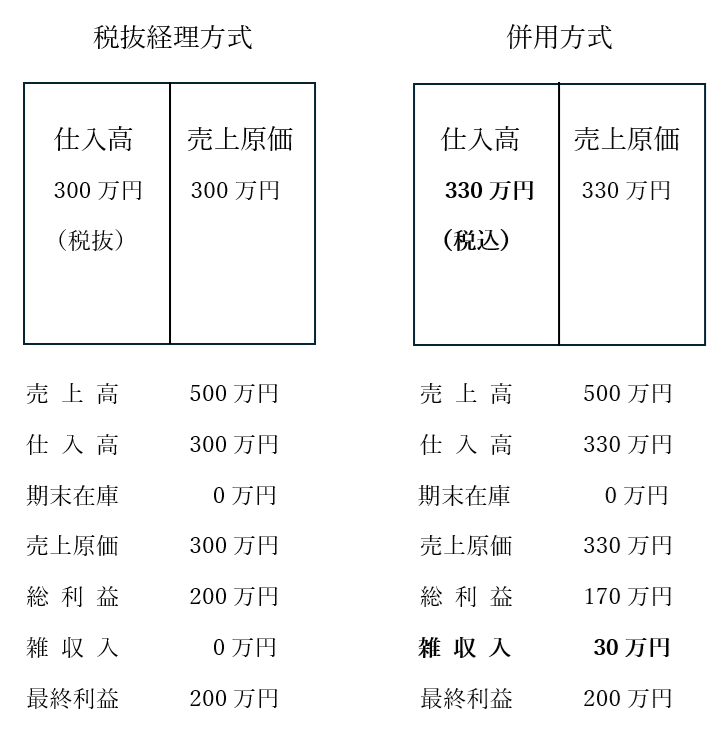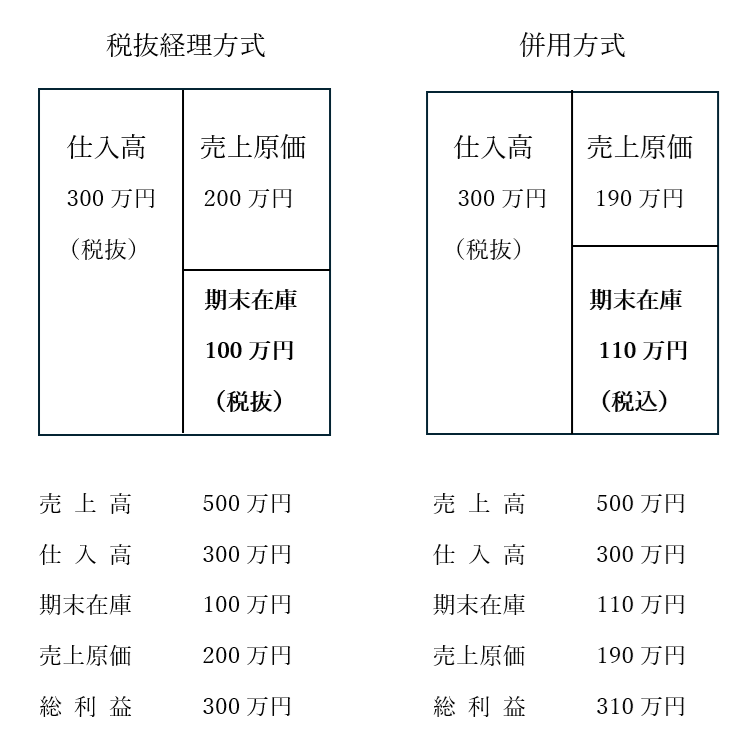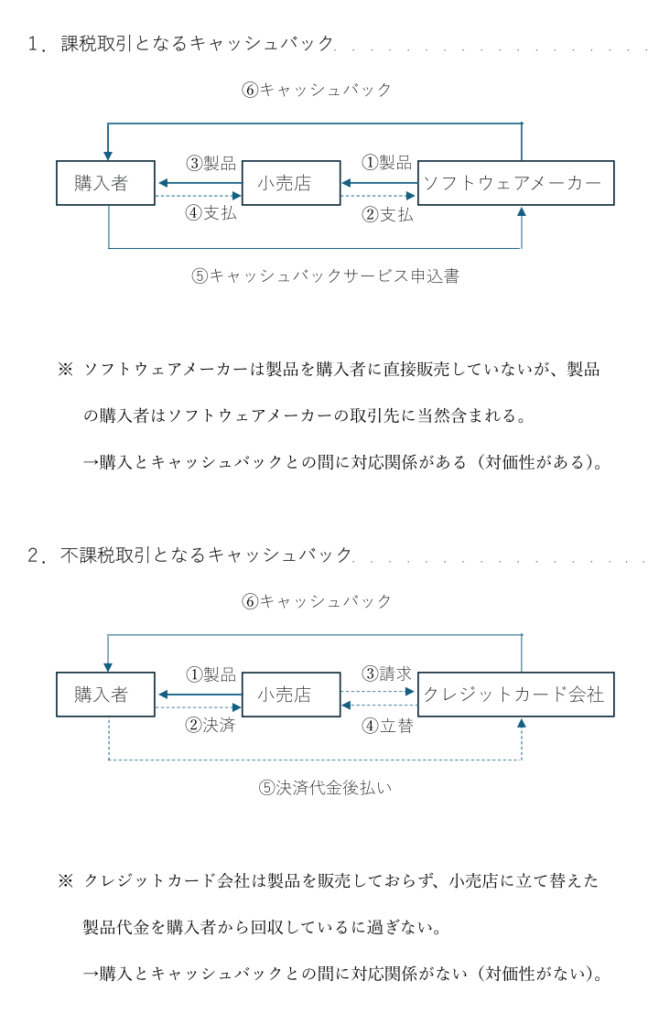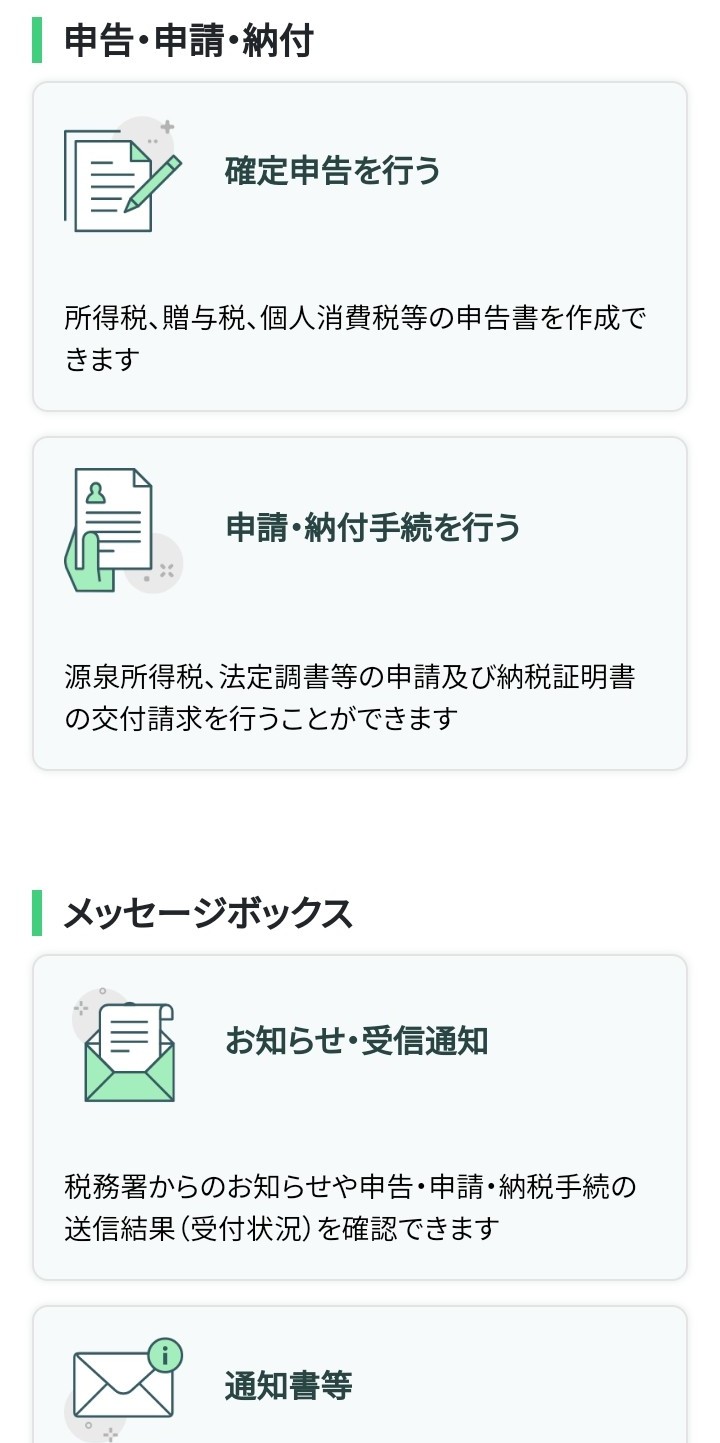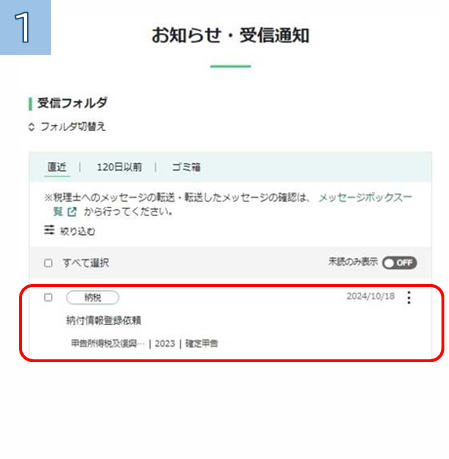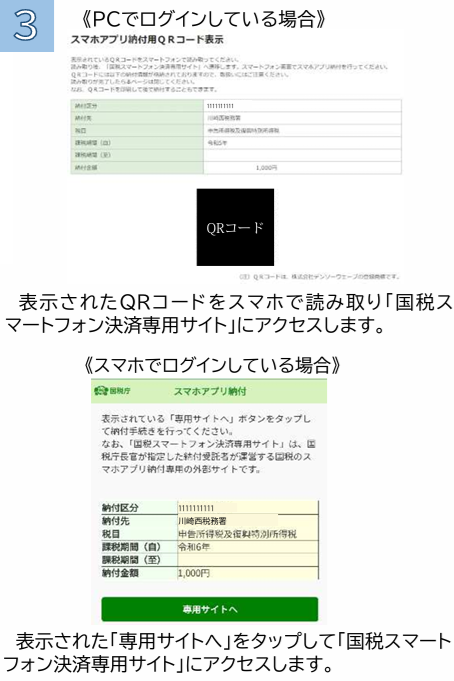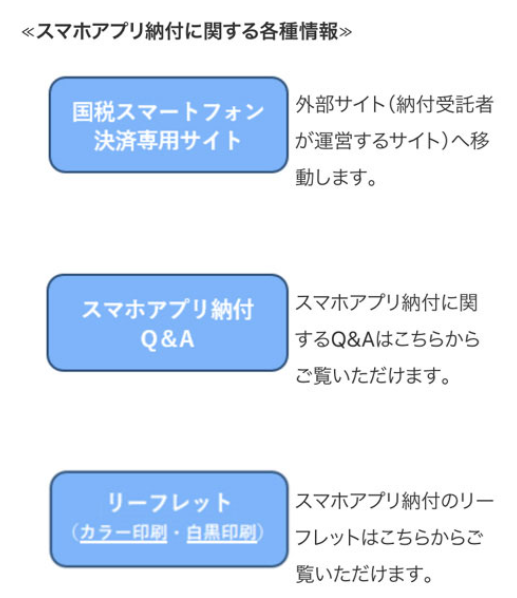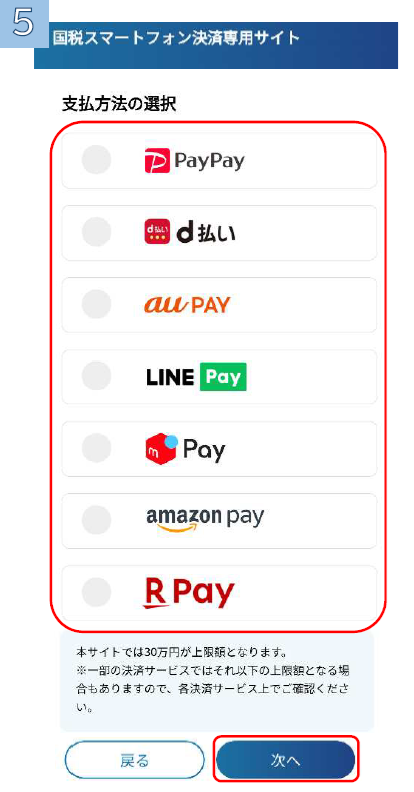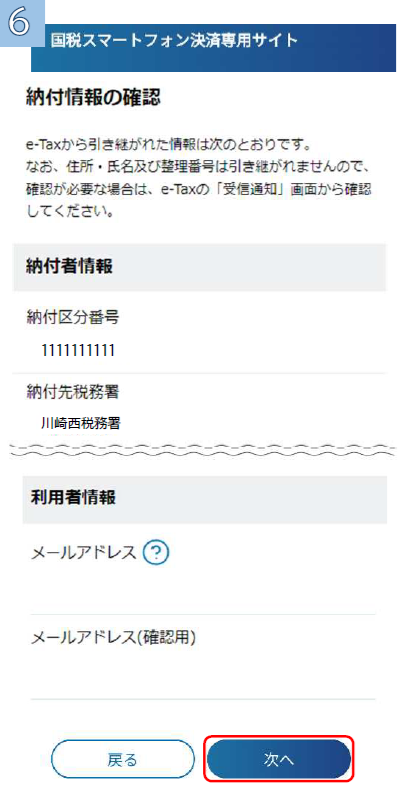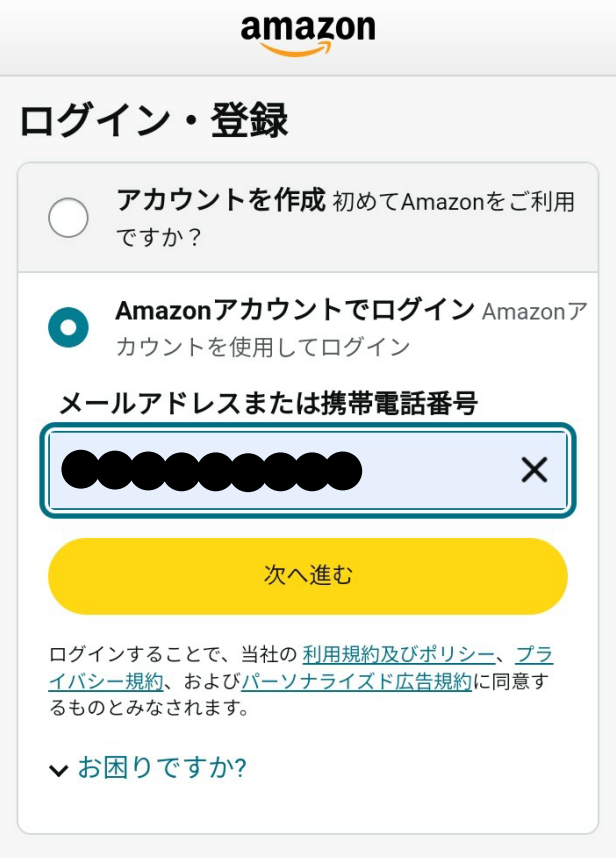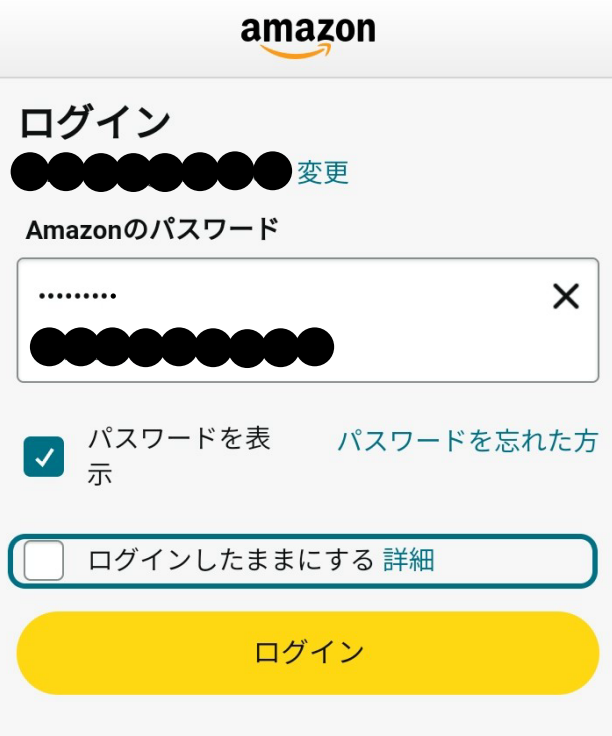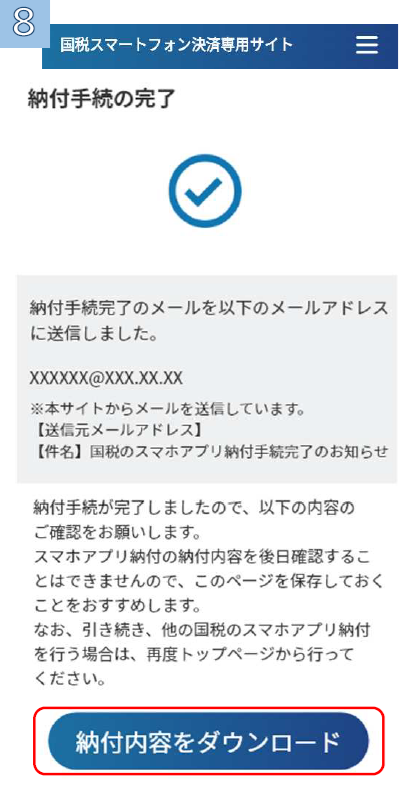消費税の仕入税額控除は、原則として課税仕入れを行った日の属する課税期間において行います。
課税仕入れを行った日とは、資産の引渡しを受けた日またはサービスの提供を受けた日をいいます。
今回は、仕入税額控除を行う時期の原則と特例について、前払金・未払金、短期前払費用、建設仮勘定を例に確認します。
1.前払金と未払金の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除の時期は、所得税や法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しを受けた日やサービスの提供を受けた日の属する課税期間とされています。
したがって、例えば、工事代金や機械の購入代金について前払金を支払っていたとしても、その前払金の支払の時期に関係なく、実際に資産の引渡しを受けた日の属する課税期間が仕入税額控除の時期となります。
同じように、工事代金や機械の購入代金について未払金があるときも、その代金の決済の時期に関係なく、実際に資産の引渡しを受けた日の属する課税期間が仕入税額控除の時期になります。
2.短期前払費用の仕入税額控除
前払費用とは、一定の契約に基づき継続的にサービスの提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち、当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていないサービスに対応するものをいいます。
この前払費用についても、原則として実際にサービスの提供を受けた日の属する課税期間が仕入税額控除の時期となります。
例えば、当期の決算日に1年分の事務所家賃を前払いしたとしても、実際にサービスの提供を受けるのは翌期になりますので、仕入税額控除の時期は翌期になります。
ところが、前払費用のうち、所得税または法人税の取扱いによりその支出した年度において必要経費の額または損金の額に算入している短期前払費用※については、特例としてその支出した日の属する課税期間が仕入税額控除の時期になります(消費税法基本通達11-3-8)。
※ 短期前払費用については、「短期前払費用の損金算入の注意点」をご参照ください。
3.建設仮勘定の仕入税額控除
建設工事の場合は、通常、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期にわたり、一事業年度を超えることがあります。
そのため、一般的には、工事代金の前払金や経費(設計料、資材購入費等)の額を一旦建設仮勘定として経理し、目的物の全部が引き渡されたときに、固定資産などに振り替える処理を行います。
消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しやサービスの提供があった日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになります。
したがって、設計料に係るサービスの提供や資材の購入等については、原則として設計業務というサービスの提供が完了した日や実際に資材の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除を行います。
ただし、建設仮勘定として計上されている金額について、その都度課税仕入れとして仕入税額控除をしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除を行う処理も特例として認められます(消費税法基本通達11-3-6)。
【原則処理】
(1) 設計料550万円支払時(当期)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 建設仮勘定 (課税仕入10%) |
5,500,000 | 現金預金 | 5,500,000 |
(2) 着手金1,100万円支払時(当期)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 建設仮勘定 (不課税) |
11,000,000 | 現金預金 | 11,000,000 |
(3) 中間金1,100万円支払時(当期)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 建設仮勘定 (不課税) |
11,000,000 | 現金預金 | 11,000,000 |
(4) 完成引渡し・残金1,100万円支払時(翌期)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 建物 (不課税) |
5,500,000 | 建設仮勘定 (不課税) |
27,500,000 |
| 建物 (課税仕入10%) |
33,000,000 | 現金預金 | 11,000,000 |
【特例処理】
(1) 設計料550万円支払時(当期)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 建設仮勘定 (不課税) |
5,500,000 | 現金預金 | 5,500,000 |
(2) 着手金1,100万円支払時(当期)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 建設仮勘定 (不課税) |
11,000,000 | 現金預金 | 11,000,000 |
(3) 中間金1,100万円支払時(当期)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 建設仮勘定 (不課税) |
11,000,000 | 現金預金 | 11,000,000 |
(4) 完成引渡し・残金1,100万円支払時(翌期)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 建物 (課税仕入10%) |
38,500,000 | 建設仮勘定 (不課税) |
27,500,000 |
| 現金預金 | 11,000,000 |
建物の建設中に支払った着手金、中間金は前払金であり資産の引渡しを受けていないため、仕入税額控除をすることはできません。
建物の引渡しを受けた時期に、仕入税額控除を行います。
一方、設計料については、原則として設計業務というサービスの提供が完了した時期に仕入税額控除を行います(【原則処理】の(1))。
ただし、建物の引渡しを受けた時点でまとめて仕入税額控除することも可能です(【特例処理】の(4))。