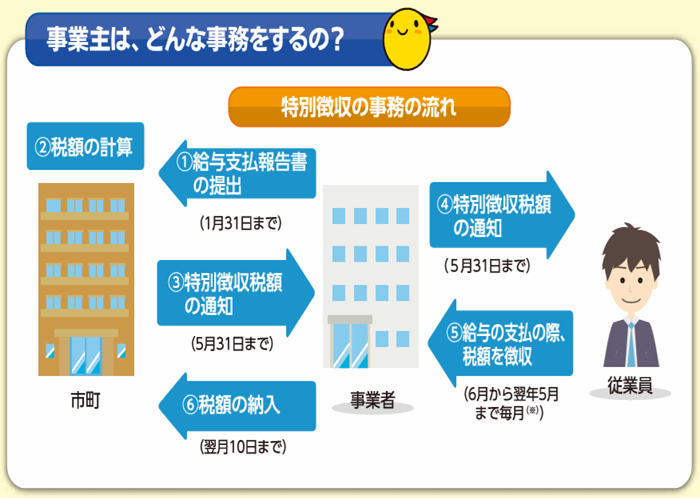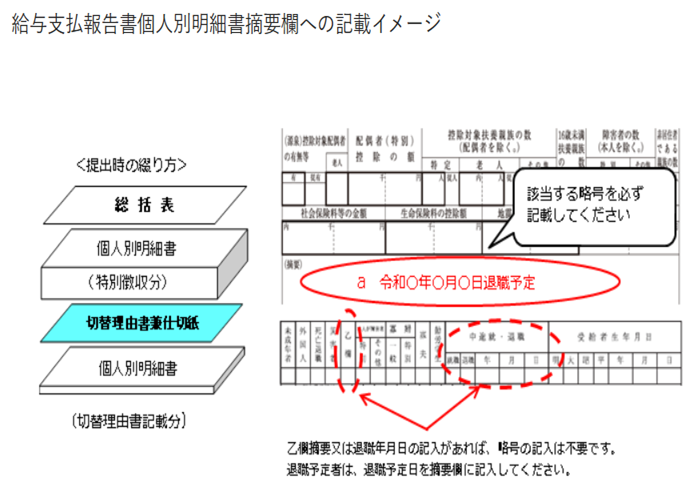償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産です。
毎年1月1日現在において償却資産を所有している法人や個人事業者は、1月31日までにその償却資産を市役所等に申告しなければなりません。
しかし、実際に申告書を作成する際には、どの資産が申告対象であるのか判断に迷うケースもありますので、以下では具体例を挙げて、償却資産の申告対象となるかどうかについて確認します。
※ 償却資産の申告対象についての基本的な考え方については、「償却資産税の申告対象となる資産とは?」をご参照ください。
1.自己所有建物に取り付けた内装など
テナント等の借家人が、その建物(借家)に内装等の附帯設備を取り付けた場合は、建物本体との附合の有無及び賃貸借契約書の内容のいかんにかかわらず、テナント等の借家人がその附帯設備を償却資産として申告する必要があります。
では、自己所有の建物に内装等の附帯設備等を取り付けた場合は、その附帯設備は償却資産の申告対象となるのでしょうか?
建物が自己所有の場合、一般的には、建物に取り付けられ建物と構造上一体となって建物の効用を高めるものについては建物の一部として取り扱われますので、その附帯設備は償却資産の申告対象ではありません。
逆に、取り外しが容易で、別の場所に自在に移動できるものや、建物と一体となっていないものは、建物とは別個に償却資産として取り扱われますので、償却資産の申告対象となります。
また、特定の生産用や業務用の設備は、建物自体の効用を高めることとは関係しないため、償却資産の申告対象となります。
なお、単に移動を防止する程度に建物に取り付けたものは、償却資産の申告対象となります。
※ 参考記事:「家屋と一体の建築設備は家屋と償却資産のどちらに該当するか?」
2.自動車に取り付けたカーナビ・カーステレオなど
自動車税や軽自動車税の課税対象となる乗用車やトラック(以下「自動車」といいます)は、償却資産の申告対象ではありません。
では、自動車に取り付けたカーナビやカーステレオなどは、償却資産の申告対象となるのでしょうか?
自己所有の車に取り付けた自己所有のカーナビ、カーステレオなどについては、性能、型式、構造等が自動車用として特別に設計され、自動車固有の装置と認められるものであれば、自動車と一体をなしているものと考えられるため、償却資産の申告対象とはなりません。
ただし、ポータブルナビゲーションのように、その使用形態が持ち運び自由な携帯型として使用することが常態となっている機器については、自動車と一体をなしているとは考えられませんので、償却資産の申告対象となります。
また、自動車の所有者と車載機器の所有者が異なる場合は、その機器は自動車そのものと一体をなしているとは認められないため、償却資産の申告対象となります。
3.家庭用にも事業用にも使用している資産
償却資産の申告対象となるのは事業用の資産です。例えば、飲食店の厨房に設置されている電気冷蔵庫は、申告対象となります。
では、家庭用にも事業用にも使用している電気冷蔵庫は、償却資産の申告対象となるのでしょうか?
家庭用にも事業用にも使用される電気冷蔵庫は、事業の用に供することができる資産であるため、その電気冷蔵庫全体が償却資産の申告対象になります。
なお、家庭用・事業用の両方に使用している場合は、資産全体の取得価格を申告する必要があります。
1つの資産を課税される部分と課税されない部分とに分けることはできませんので、ご注意ください。