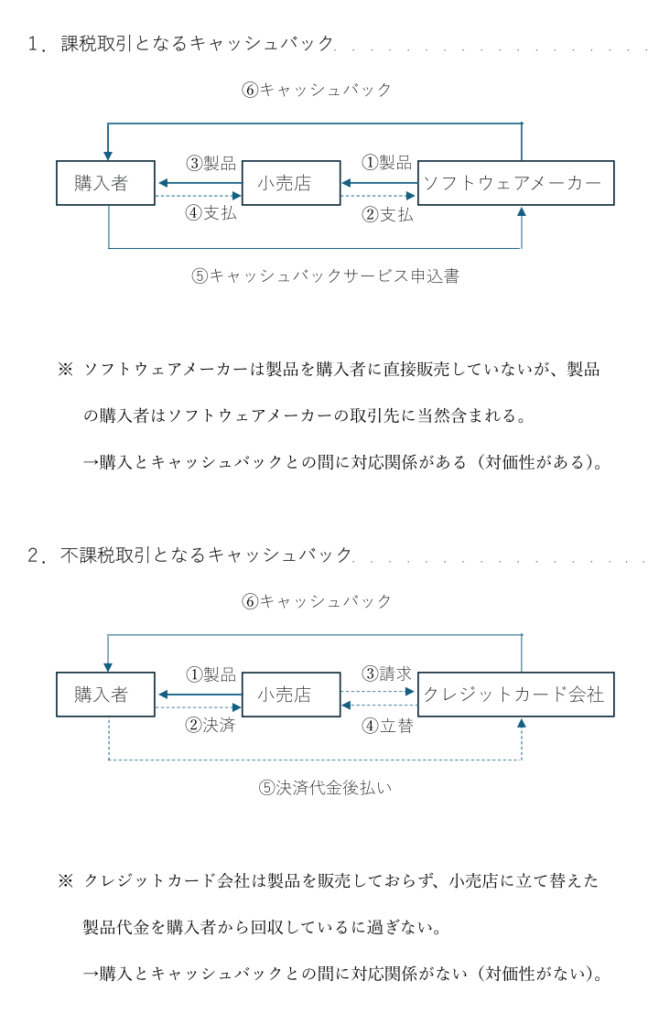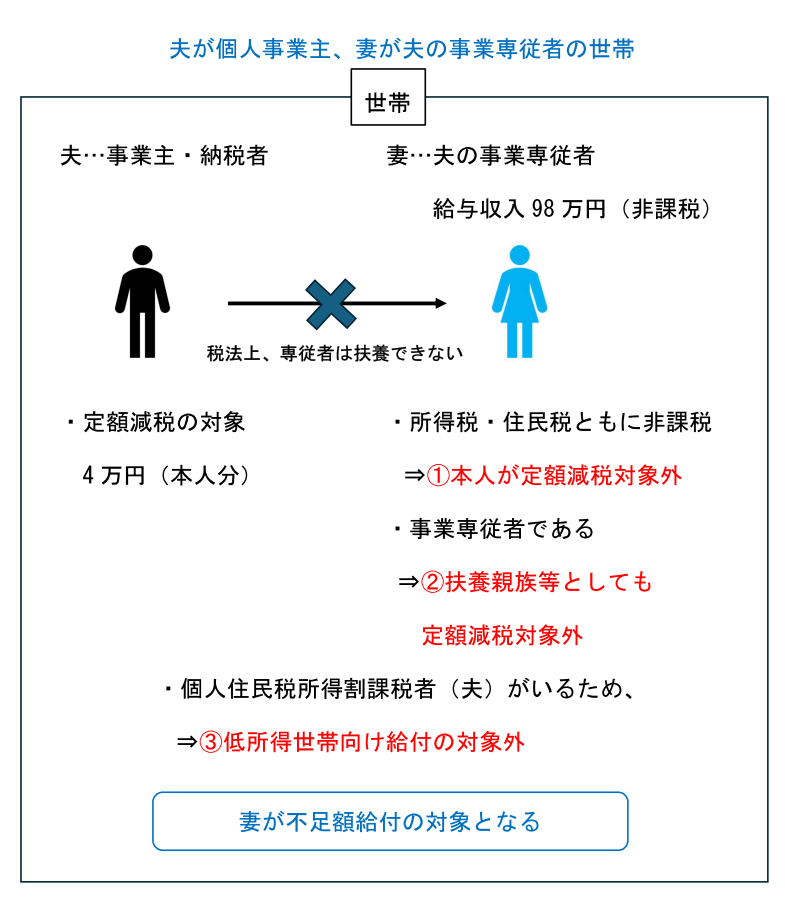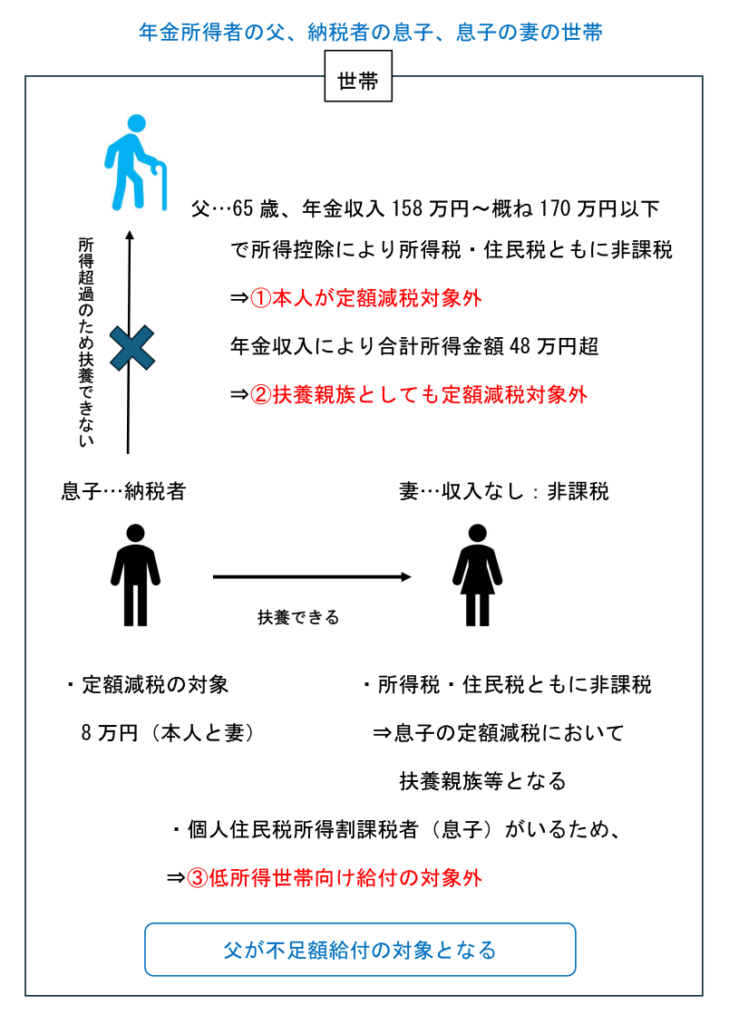2025(令和7)年度税制改正※では、所得税の基礎控除や給与所得控除の引き上げ等が行われましたが、これに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が見直されました。
また、住宅借入金等特別控除や生命保険料控除についても見直しが行われていますので、以下ではこれらについて確認します。
※ 令和7年度税制改正の内容については、「基礎控除・給与所得控除の引き上げと源泉徴収事務・年収の壁への影響(令和7年度税制改正)」、「特定親族特別控除の創設と源泉徴収事務への影響(令和7年度税制改正)」、「令和7年度税制改正で年収の壁はこのように変わった!」をご参照ください。
1.扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の改正に伴い、扶養控除、配偶者控除、ひとり親控除、障害者控除、寡婦控除、配偶者特別控除、勤労学生控除の対象となる扶養親族等の所得要件が、下表のように改正されました。
| 扶養親族等の区分 | 改正前の所得要件※1 | 改正後の所得要件※1 |
|---|---|---|
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
48万円以下 (103万円以下)※2 |
58万円以下 (123万円以下)※2 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 (103万円超201万5,999円以下)※2 |
58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下)※2 |
| 勤労学生 | 75万円以下 (130万円以下)※2 |
85万円以下 (150万円以下)※2 |
※1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。合計所得金額、総所得金額等については、「『合計所得金額』『総所得金額』『総所得金額等』の違いとは?」をご参照ください。
※2 表中のカッコ内の金額は、収入が給与だけの場合の収入金額です。特定支出控除の適用がある場合は、表の金額とは異なります。
2.住宅借入金等特別控除の改正
子育て世帯・若い夫婦世帯※1が、①認定住宅等※2の新築、②認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得、③買取再販認定住宅等※3の取得をして、2025(令和7)年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の借入限度額を次のとおりとして、所得税額の特別控除が適用できることとされました。
| 住宅の区分 | 改正前の借入限度額 | 改正後の借入限度額 |
|---|---|---|
| 認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
※1 子育て世帯・若い夫婦世帯とは、年齢19歳未満の扶養親族のいる世帯又は夫婦のいずれかが年齢40歳未満の世帯をいいます。
※2 認定住宅等とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいいます。認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
※3 買取再販認定住宅等とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいいます。
また、①認定住宅等の新築、②認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和(原則50㎡)する措置が、2025(令和7)年12月31日以前(改正前は2024(令和6)年12月31日以前)に建築確認を受けた家屋について適用できることとされました。
なお、これらの住宅借入金等特別控除に関する今回の改正は、2025(令和7)年限りの時限的措置となっています。
3.生命保険料控除の改正
生命保険料控除について以下の見直しが行われたほか、所要の措置が講じられました。この改正は、2026(令和8)年分の所得税について適用されます(2026(令和8)年分のみの適用)。
(1) 新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除の控除額は、次のとおり計算することとされました。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
(2) 旧生命保険料及び上記(1)の適用がある新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前は4万円)とされました。
なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、現行と同様の12万円となります。