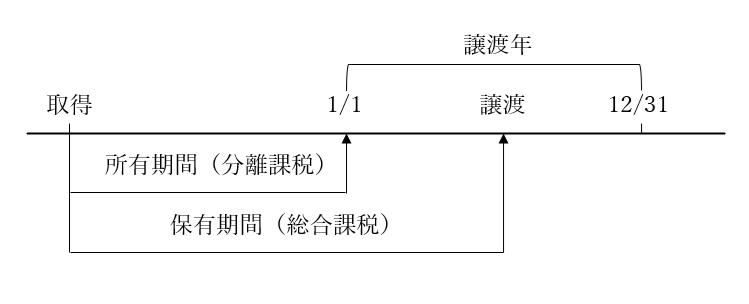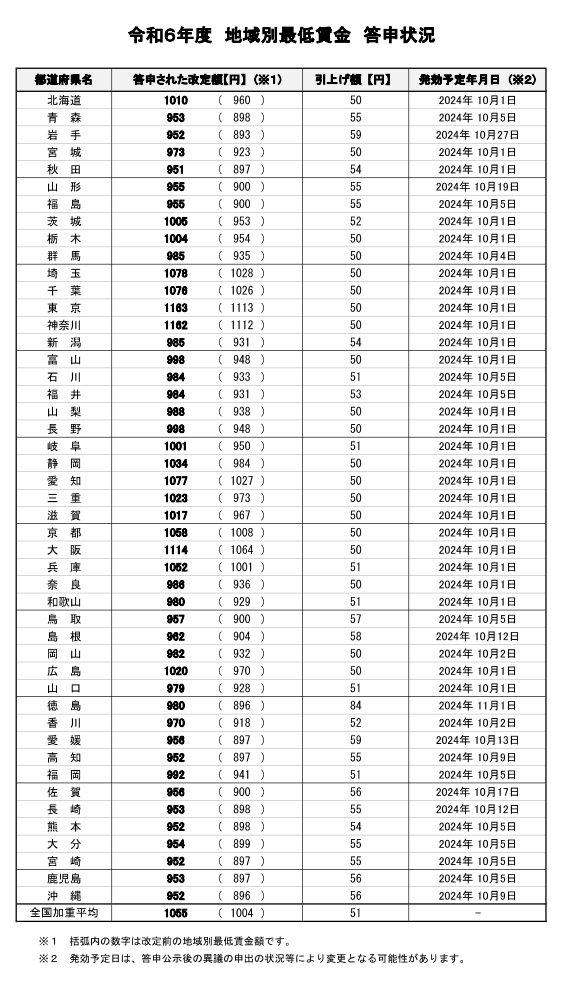2024(令和6)年度税制改正で、交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準が「1人当たり10,000円以下(改正前:5,000円以下)」に引き上げられました。
以下では、この1人当たり10,000円以下の飲食費について確認します。
1.交際費等とは?
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます)のために支出するものをいいます。
これらの交際費等は、会計上はその事業年度の費用として処理されますが、法人税の所得計算上は一定限度額までしか損金に算入されません。
2024(令和6)年4月1日以後開始事業年度の交際費等の損金算入額は、下表のとおりです(表中における「接待飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用で、専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するもの(社内飲食費)を除きます)。
| 企業規模 | 損金算入額 |
|---|---|
| 期末の資本金又は出資金の額が1億円以下の法人 ※ 資本金又は出資金の額が5億円以上の会社の100%子会社等は、1億円超の法人と同じ取扱いとなります。 |
次のいずれかを選択できます。 (A)交際費等のうち、接待飲食費50%相当額以下の金額 (B)交際費等の金額の年800万円(定額控除限度額)以下の金額 |
| 期末の資本金又は出資金の額が1億円超の法人 | 交際費等のうち、接待飲食費50%相当額以下の金額 |
| 期末の資本金又は出資金の額が100億円超の法人 | なし |
2.交際費等の範囲から除かれるもの
上記1のように、交際費等の損金算入には一定の制限がかかりますが、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。つまり、損金算入の制限はありません。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(3) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(4) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
(5) 1人当たり10,000円以下の飲食費
上記(5)の金額基準が、2024(令和6)年度税制改正において、1人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。
3.1人当たり10,000円以下の飲食費とは?
1人当たり10,000円以下の飲食費とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用をいいます。
ただし、専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するもの(社内飲食費)を除きます。
また、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項(その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項)
なお、1人当たり10,000円以下の飲食費の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。
4.飲食費に該当するもの・しないもの
上記3の飲食費については、租税特別措置法に「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)」と規定されています。
したがって、次のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当します。
(1) 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
(2) 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
(3) 飲食等のために支払う会場費
(4) 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
(5) 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
一方、次の費用は飲食費に該当しません。
(1) ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用※
(2) 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
(3) 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
※ 飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合、例えば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合などは、飲食費に該当します。
5.保存書類への参加者の氏名等の具体的な記載方法
上記3(2)で見たように、1人当たり10,000円以下の飲食費の規定の適用要件として、「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」を記載した書類を保存しなければなりません。
これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というように、原則として、相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えないものとされています(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略しても差し支えありません)。
また、その保存書類の様式は法定されているものではありませんので、記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式で作成して差し支えありません。
なお、一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は仮装に当たりますのでご注意ください。