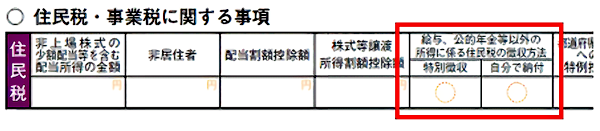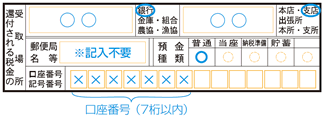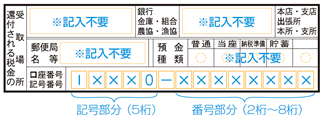住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)は、新築住宅から中古住宅、増改築まで幅広く適用があります。
中古住宅の場合は住宅ローン控除を受けられないと思っている方も見受けられますが、要件を満たせば適用を受けることができますので、確定申告をして税負担を軽くしましょう。
個人が中古住宅を取得した場合で、次の1~5の要件をすべて満たすときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
※ 2021(令和3)年度税制改正で、住宅借入金等特別控除制度について床面積要件等の見直しがされています。改正内容については、本ブログ記事「住宅借入金等特別控除の適用要件等の見直し」をご参照ください。
1.家屋等に関する要件〈築年数等〉
取得した中古住宅が、次の(1)~(4)のいずれにも該当する住宅であること
(1) 建築後使用されたものであること
(2) 次の①~③のいずれかに該当する住宅であること
① 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物※の建物の場合には25年)以下であること
※ 「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
② 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること※
※ 次の証明書等が付された家屋の場合は、上記①の築年数の要件を満たすものとされます。
イ.耐震基準適合証明書(家屋取得の日前2年以内に証明のための調査が終了したもの)
ロ.建設住宅性能評価書(評価等級が1~3のもの)の写し(家屋取得の日前2年以内に評価されたもの)
ハ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(家屋取得の日前2年以内に締結されたもの)
③ 2014年(平成26年)4月1日以後に取得した中古住宅で、上記①又は②のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項又は41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項若しくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること
(3) 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと
(4) 贈与による取得でないこと
2.家屋等に関する要件〈床面積〉
取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること※
※ この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
(1) 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
(2) マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
(3) 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
(4) 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
3.取得者に関する要件
次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1) 取得者は居住者であること(2016年(平成28年)4月1日以後の取得については、非居住者でも可)
(2) 取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること※
※ 個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいれば適用を受けることができます。
※ 中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅借入金等特別控除については、新型コロナウイルス感染症の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の適用要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、次の①~③の要件を満たすときは、その適用を受けることができます(新型コロナ税特法6条、新型コロナ税特令4条)。
① 中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日又は新型コロナ税特法の施行の日(2020年(令和2年)4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日までに、増改築等の契約を締結していること
② 増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること
③ 2021年(令和3年)12月31日までに中古住宅に入居していること
(3) この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額※が、3,000万円以下であること
※ 合計所得金額とは、次の①~⑦の合計額をいいます。
① 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額
② 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
③ 株式等に係る譲渡所得等の金額
④ 上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)
⑤ 先物取引に係る雑所得等の金額
⑥ 山林所得金額
⑦ 退職所得金額
4.借入金に関する要件
10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます)があること※
※ 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%(2016年(平成28年)12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
5.重複適用排除の対象となる譲渡所得の特例
取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の(1)(2)の期間において、その取得をした家屋及びその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例※の適用を受けていないこと
(1) 2020年(令和2年)4月1日以後に譲渡した場合
その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間
(2) 2020年(令和2年)3月31日以前に譲渡した場合
その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間
※ 重複適用排除の対象となるのは、以下の譲渡所得の特例です。
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)
・居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)
・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2、36の5)
・既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)