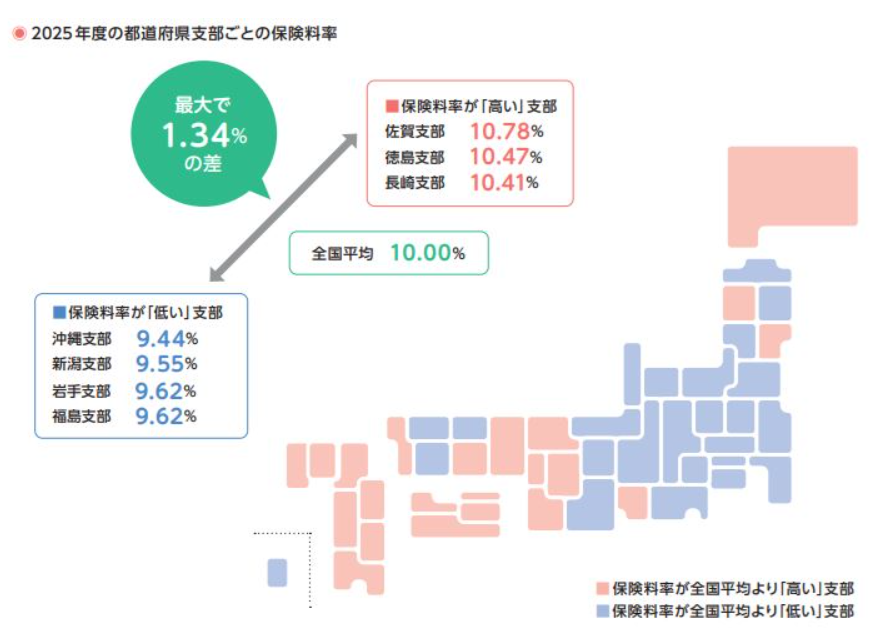1.月額8万円の専従者給与は所得税・住民税・事業税の節税になる
生計を一にしている配偶者その他の親族が個人事業主の経営する事業に従事している場合、個人事業主がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、青色申告を行っている個人事業主の場合は、これらの人に実際に支払った給与の額を一定の要件の下に必要経費とすることができます。これを青色事業専従者給与の特例といいます。
青色事業専従者給与は青色申告の特典の一つであり、個人事業主自身の所得税・住民税・事業税の節税になりますが、その一方で気になるのが、給与の支払いを受けた青色事業専従者には、その支払いを受けた給与の分だけ給与所得が生じ、所得税負担がかかる可能性があるということです。
この点については、例えば青色事業専従者給与の額を月額8万円にすれば、青色事業専従者自身に所得税・住民税負担がかかることはありません。
つまり、月額8万円の青色事業専従者給与を支給することは、個人事業主自身の節税になり、青色事業専従者自身の税負担もないということです。
ところが、ここでさらに気になるのが、月額8万円の青色事業専従者給与の支給が国民健康保険税に及ぼす影響です。所得税・住民税・事業税の節税にはなっても、その分国民健康保険税が上がりはしないかという懸念があります。
以下では、青色事業専従者給与が国民健康保険税に及ぼす影響を検討します。
2.国民健康保険税の計算の仕組み
国民健康保険税の計算の仕組みは各自治体で異なるため、以下では兵庫県宝塚市の2023(令和5)年度の例を挙げます。
| A.基礎課税額 |
|
| (1) 平等割額(1世帯あたり) |
23,900円 |
| (2) 均等割額(被保険者1人あたり) |
31,600円 |
| (3) 所得割額の税率(被保険者全員の所得に対して) |
8.40% |
| (4) 課税限度額 |
65万円 |
| B.後期高齢者支援金等課税額 |
|
| (1) 平等割額(1世帯あたり) |
6,200円 |
| (2) 均等割額(被保険者1人あたり) |
8,900円 |
| (3) 所得割額の税率(被保険者全員の所得に対して) |
2.20% |
| (4) 課税限度額 |
22万円 |
| C.介護納付金課税額 |
|
| (1) 平等割額(1世帯あたり) |
6,200円 |
| (2) 均等割額(介護保険第2号被保険者1人あたり) |
12,100円 |
| (3) 所得割額の税率(介護保険第2号被保険者全員の所得に対して) |
2.70% |
| (4) 課税限度額 |
17万円 |
国民健康保険税額は、上記のA~C の合計額です。A~Cをそれぞれ別々に納付することはできません。また、納税義務者は被保険者の属する世帯の世帯主です。
C の介護納付金課税額は介護保険第2号被保険者(40歳~64歳の被保険者)がいる世帯に対してかかります。
A~Cにおける(3) の所得割額は、被保険者ごとに前年中の総所得金額等から地方税法上の基礎控除額(43万円)を控除した後の金額(算定基礎額)に税率をかけて算出します。例えば、総所得金額が120万円の場合は、120万円-43万円=77万円が算定基礎額となり、これに税率をかけて所得割額を算出します。
次の設例を用いて、2023(令和5)年度の国民健康保険税の計算をしてみます。
事業主:健康太郎 1977(昭和52)年4月23日生 前年の事業所得120万円
配偶者:健康花子 1980(昭和55)年1月23日生 専業主婦 |
| A.基礎課税額(課税限度額650,000円) |
| (1) 平等割額(1世帯あたり):23,900円/年 |
| (2) 均等割額(1人あたり):31,600円×2人=63,200円/年 |
| (3) 所得割額の税率:770,000円×8.40%=64,680円/年 |
| (4) 基礎課税額合計:(1)+(2)+(3)≒151,700円/年(百円未満切捨) |
| B.後期高齢者支援金等課税額(課税限度額220,000円) |
| (1) 平等割額(1世帯あたり):6,200円/年 |
| (2) 均等割額(1人あたり):8,900円×2人=17,800円/年 |
| (3) 所得割額の税率:770,000円×2.20%=16,940円/年 |
| (4) 基礎課税額合計:(1)+(2)+(3)≒40,900円/年(百円未満切捨) |
| C.介護納付金課税額(課税限度額170,000円) |
| (1) 平等割額(1世帯あたり):6,200円/年 |
| (2) 均等割額(1人あたり):12,100円×2人=24,200円/年 |
| (3) 所得割額の税率:770,000円×2.70%=20,790円/年 |
| (4) 基礎課税額合計:(1)+(2)+(3)≒51,100円/年(百円未満切捨) |
| D.国民健康保険税額 |
| 国民健康保険税額:A+B+C=243,700円/年 |
3.専従者給与は国民健康保険税の節税になる
上記2の設例では、事業主の総所得金額(事業所得)が120万円で配偶者の所得が0円の場合の国民健康保険税を試算しました。
次に上記2の設例において、配偶者に月額8万円(年額96万円)の青色事業専従者給与を支給する場合の国民健康保険税を以下で試算します。
この場合、事業主の事業所得は120万円-96万円=24万円になり、配偶者の給与所得は96万円-55万円(給与所得控除額)=41万円となります。
事業主:健康太郎 1977(昭和52)年4月23日生 前年の事業所得24万円
配偶者:健康花子 1980(昭和55)年1月23日生 前年の給与所得41万円 |
| A.基礎課税額(課税限度額650,000円) |
| (1) 平等割額(1世帯あたり):23,900円/年 |
| (2) 均等割額(1人あたり):31,600円×2人=63,200円/年 |
| (3) 所得割額の税率:0円×8.40%=0円/年 |
| (4) 基礎課税額合計:(1)+(2)+(3)≒87,100円/年(百円未満切捨) |
| B.後期高齢者支援金等課税額(課税限度額220,000円) |
| (1) 平等割額(1世帯あたり):6,200円/年 |
| (2) 均等割額(1人あたり):8,900円×2人=17,800円/年 |
| (3) 所得割額の税率:0円×2.20%=0円/年 |
| (4) 基礎課税額合計:(1)+(2)+(3)≒24,000円/年(百円未満切捨) |
| C.介護納付金課税額(課税限度額170,000円) |
| (1) 平等割額(1世帯あたり):6,200円/年 |
| (2) 均等割額(1人あたり):12,100円×2人=24,200円/年 |
| (3) 所得割額の税率:0円×2.70%=0円/年 |
| (4) 基礎課税額合計:(1)+(2)+(3)≒30,400円/年(百円未満切捨) |
| D.国民健康保険税額 |
| 国民健康保険税額:A+B+C=141,500円/年 |
上記の試算より、配偶者に青色事業専従者給与を支給する場合の国民健康保険税は141,500円/年となり、支給しない場合の243,700円/年より減額されています。
つまり、月額8万円の青色事業専従者給与の支給は、所得税・住民税・事業税だけではなく、国民健康保険税にも節税効果があることがわかります。また、青色事業専従者の税負担も生じていません。
上記の試算では、青色事業専従者である配偶者に税負担を生じさせないという前提で、所得税・住民税・事業税・国民健康保険税の節税効果を狙って月額8万円の給与としました。
どの程度の給与を支給するかについては、個人事業主と青色事業専従者の年齢やそれぞれに適用される所得税率を考慮しながら最適解を探ることになります。
なお、青色事業専従者として給与を支給された配偶者は、国民年金保険料の免除申請等を行う際の「扶養親族等」には含まれなくなります。
国民年金保険料は所得にかかわらず一律ですが、もし免除申請等を行う際は不利になる場合もありますのでご注意ください(国民年金保険料の免除ラインについては、本ブログ記事「国民年金保険料が免除される所得基準の計算方法~確定申告書との違いに注意!」をご参照ください)。